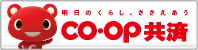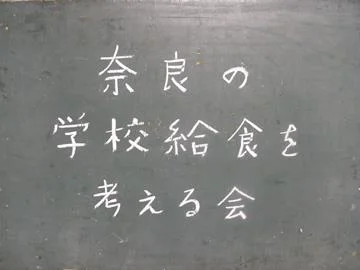2-4おいしいのチカラ
阿南 2つあるとおっしゃったと思いますけど、もうひとつも触れていただいていいですか。
三浦 はい。いまのは社会課題とレストランの魅力づくりをデザインした課題解決の方法になります。夏目漱石の「草枕」には「智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。義を重んずれば窮屈だ」とありますが、100年前にすでに「人間って伝え方に3つあって、それぞれに利点もあるし弱点もありますよ」といわれていました。特に農作物のところっていうのは、食の安定供給を語られるときにはたぶん正論で、知識で語れることが多いと思います。 ところが農家さんを援助しようとか子どものためにというように、情を通じて語ると広がりがあるような気がしますし、義というのはルールだとか義務だとか、田舎に行ったら「田畑荒れたらあかんから」とかそういう使命感で縛る等々。 どれも大切なんですけども、それぞれ利点もあり弱点もある。
それで、4つ目のアプローチがあるんじゃないかと考えています。11年前に書いた1冊目の本のなかでも述べているとおり、伝統野菜を30年研究してきた結果、いろんなところに聞き取り調査に行ったきた中で、あることに気がつきました。実は伝統野菜を作ってらっしゃるみなさん、健康寿命が長い方が多いです。それから家族仲いい方も多いです。それに周りには生物多様性が豊かです。さらに地域の結びつきも強い。いまでいうコミュニティとか、助け合いの自給率が高いんですね。これはどこの方とお会いしてもそんなかんじでした。あともう一つこれは余談なんですけれども、会社で出世している方が多いです。
伝統野菜を作ってこられた理由は、みなさん「美味しくて作りやすいから」という理由です。美味しいというのは儲かるではなくて家族が好きだからとかそういう嗜好性を大事にすること。作りやすいということは気候風土に合っているということ。この2つを追求して生まれたのが伝統野菜です。
みなさん「ブルーゾーン」という言葉をご存じでしょうか。ブルーゾーンとは、100歳以上の方が多く、健康寿命が長い地域のことです。世界に5か所あるんですけど、20年前の沖縄もその当時はブルーゾーン地域だったのです。日本はいま寿命が世界でいちばん長い国で84歳です。ところが健康寿命ってそこから約10年低いんですね。要するに最後はみなさん病気になり、要介護や寝たきりになっているということです。ここを最後まで健康で行かれる方が非常に多いのがこのブルーゾーンといわれてる地域です。イタリアのサルデーニャ島等が有名ですけれども、実は日本にも沖縄があって、私がそこで得た知見というのは、このブルーゾーンと同じ原理があるのではないかと思っています。
ということで、伝統野菜、地元の農作物を栽培しているというのが世界の長寿地域ブルーゾーンとの共通の特徴になっていまして、こういったことを少し意識して取り入れていくと、消費者と生産者が一体になっていくというか、その距離の壁を少しずつ下げていく、それが農作物の魅力を別の角度から伝えることにつながりますし、自分たちがそこに貢献していくことにもつながっていくのではないかと思いまして、この2つの事例を挙げさせていただきました。
阿南 ありがとうございます。オオニシ先生、三浦さんのお話を伺われて、いかがですか。
オオニシ そうですね。結局体の問題に苦しむことなく自分の人生を終えられるのが究極の幸せにつながるかなと思うんですけど、その食べ物はおいしくなくちゃいけないわけです。そして自分の体の役に立ってくれないと困るわけなんですけど、その原点は農にあると私も思います。ですから、農業の担い手がだんだん減っていくという現在の問題はすごく大変な問題ですよね。だから農家さんというのは特殊な職業なのではなく、みんながやり出すというのはいいんではないかと思いますね。昔は自分の家の裏にみんな畑があるような。ヨーロッパでは意外とふつうの人がみんな自分の野菜を作ってますしね。
阿南 その点、いつも「小さな農業」という言葉でいろいろと提唱なさっている三浦さんいかがですか
三浦 オオニシ先生がおっしゃったところだと思ってます。先生はヨーロッパの知見が広いですからヨーロッパでそういう地域がたくさんあるとおっしゃいましたけど、実は奈良でもちょっと昔、昭和30年代くらいは当たり前に自分の食べる野菜は自分で作っていて、もしくは自分のところに畑がなくても親戚関係やコミュニティでシェアしあう文化がありました。沖縄はだんだん崩れてはきてますけども、何が原因で崩れているのかを理解すると、もう一度紡いでいけるのかなという気がしています。
オオニシ 沖縄は以前は長寿で、日本のなかでも一番でしたね。それがもう20何位まで落っこちたっていう話で、その原因はファストフードが入ってきたからだと言われてますでしょ。だから奈良が伝統野菜とか伝統的な食べ物を見直すということを推進していくのはいちばんじゃないかなと思いますね。
三浦 オオニシ先生のところに勉強に行かれる方っていうのは、どういった方がいらっしゃるんですか。
オオニシ いろいろな方がおりますけど、いま圧倒的に多いのが40代から50代くらいの方で、やはり自分の家族を守りたいという意識がある方が来ていますね。
三浦 自分の家族を守りたいということは、ご自身もそうですし、自分の家族のためにより良い食を活かした、体にも寄与する料理方法を勉強したい、知恵を学びたいという方ですね。
オオニシ ええ。自分が何を食べたらいいか、それをすごく熱心に知りたいという方が多いです。
阿南 おいしいから食べる、家族が喜ぶ、その結果が長寿っていう健康につながり、オオニシ先生の場合はすでに体調不良とか課題があったときにそれを単純に病院に行くんではなくて食を見直して、食に立ち戻って。
オオニシ 体にいいっていうとまずいんでしょみたいなイメージが前はあったんですけどね、でもそうじゃなくて、自分の体に合ってるものは本当においしいって感じるはずなんですよ。
阿南 それはあると思います。肉体労働の人って塩味の濃いのが好きなんですよね。汗をかかれる方は塩を求めるから、やっぱり求めたものをおいしく感じるっていうのは誰でもあることですよね。
オオニシ そうですよね。究極でやっぱり食べることはおいしくなくちゃいけないと私は思っているんですね。これが体にいいからまずくても我慢して食べるっていうことはほとんどないんです。例えばみなさんごぼうのすり下ろしたのを生で食べてくださいって言われたら、えーなんかまずそうーと思いますでしょ。ところがそれが必要な人はごぼうのすりおろしを飲みますと、腹水が溜まって困ってる人がとるとぺっちゃんこになるとか、体中アレルギーでかゆいっていう人がごぼうのすりおろしをとりますと解毒作用がすごく激しいので案外治っちゃうんですね。そういう人が摂りますとね、おいしいっていうんですよ。私もはじめ自分が食べてないから、まずいけど我慢してごぼうのおろしとると効くからとってくださいねって言ってたんですけどね。あとからまずかったでしょってきいたら、いやすごくおいしかったですって。それから卵から取り出した卵油っていうのがあります。それもおいしそうなスクランブルエッグを通り越してさらに1時間以上焦がしていきますと真っ黒の塊になっていくんですね。煙がもうもう出て、そこから急に油が出てくるんですが、それを取り出したのが卵油といいまして、心臓の妙薬なんですね。心臓の弱い人は先天性の心臓の問題でも治ってしまったというくらいの実績のある卵油なんですが、私なんかはいまそんな問題はないので、それちょっと舐めるとわーにがい、まずいと思うんですが、心臓の悪い人がそれを摂るとおいしいっていうんですね。チョコレートみたいだっていうんで、えーそうですかっていうことになっちゃうんですけど。その人その人の体が必要としているものがあって、それをとりますと、みんな必要だから体がアクセプトしろということになりまして、おいしいということになるんです。だからおいしいということは大事なんですけど、ただおいしいと言っても、舌先だけのおいしさなのか、体が本当に喜ぶおいしさなのかの違いはあると思います。
阿南 味覚も変わってきているそうで、いまの子どもたちは生まれたときから化学調味料や加工食品に囲まれて生きているので、自然な味付けのものを最初味気ないって思ったりすることもあるって聞いてるんですね。だから子どもたちにこそオーガニックなものを、体ができあがるいちばん大事なときに、人生でいちばんお金のかかる時期でもあるんですけれども、ここはやっぱり子どもさんのために食で楽しさと健康を作っていってあげれたらどんなにいいかなというふうに思いますね。日本人はもともと農業とともに生きてた人たちだったんですよ。今のほうが歴史的にみてちょっと瞬間的に異常な状態で、本当に縄文時代から農業はやってましたから。水田のほうの稲作は弥生からですけどね。だから本当に農イコール日本人っていうくらいだったわけですよ。
いまどうしてこんなに農業が衰退しているかっていうと、国策といえばそれまでなんですけれども、農業は「儲かる」という言葉とすごく似合わない業界なんですよね。でもみんな儲かるのが好きだから、農家の長男さんとかが、収入が心配だからほかのお前は公務員になれとか言って育てられるわけですよ。でも「畑活」みたいな売らない小さな農業というのは、それで儲けようというのとはまた違うんですよね。それでオーガニックなものを自分で作れて、それがオオニシ先生が指導されているように、いま自分にとって必要なものを食べることで医療費も下がって、薬代も下がって、浮いたお金で粟さん行って美味しいもの食べて、みたいな。そういうところでいい循環ができると、これがプロの農家のみなさんへのまた気づきになっていくんじゃないかなと思います。
要は、食べる人っていうのは消費者ですよね。消費者が何を求めているのかがマーケットを決めますよね。ですから、いいもの、オーガニックなものをちゃんと選ぶ人が増えれば増えるほど、慣行農法を含めて日本の農業や農地を守ることにつながるんじゃないかなあというふうに、お二人のお話を聞いてて今日は思いました。それではお二人から最後のメッセージをお願いします。
三浦 すみません、なかなか突飛なことをお伝えしてしまったので、なんともという感じかもしれませんけれども、さきほどブルーゾーンのところでお話させていただいたことに少し補足させていただきます。天岩戸開き作戦っていうのは、結局正しいからとか正義だからではなく、こっちに来たほうがよりWell-beingが高くなったりとか、幸せになったりとか、阿南さんもおっしゃったように実は健康になるとか、それも副産物ですけどね、結果的にそれがついてくるみたいなライフスタイルに農は不可欠だというところに結びついてます。そして、ブルーゾーンの共通項として何があるのかということですが、その共通項は分かりやすくて次のようなこととされています。適度な運動、別にライザップをこなす必要はありません。あとは腹八分目で食べること。それから全粒の穀物と、とにかく自家生産の野菜をたくさん食べること。そしてそれはポリフェノールを多く含む在来品種が多いようです。沖縄では当たり前のように伝統野菜が耕作されてました。あとは、家族を大切にするとか、人とつながるみたいなこともあるんですけれども、そういったところがブルーゾーンの共通項ということで、「畑活」をすると自然とつながっていくことばかりです。もう一度日本にも昔あった農のスタイル、農業のスタイルではなく「農的な暮らしのスタイル」を見つめなおしてみる、その副産物も見つめなおしていくきっかけに今日のこの機会がなればいいなと思っています。ありがとうございました。
オオニシ 戦後、日本が戦争に負けたということが日本をダメにしてしまった、その傷が今でも続いてるということを私は実感してるんですけども、それを超えて日本をもういっかい取り戻すための原点は、やっぱり農業とか食べるものだと思います。だから自分の体を養っている材料にもっとお金をかけてもいいんじゃないかと思うんですね。安いもの、外国から買ったほうが手っ取り早い、安いじゃなくて、自分の命をどうやって養うか、自分の体がどうなってるかとか、自分の身の回りに生えてる植物や野菜たちがどんなふうに自分と関係性が持てるのか。本当に野菜とか周りの植物たちって知れば知るほど拝みたくなるほどパワフルで私たちを助けてくれる要素をたくさん持ってるので、そういうことをみなさんにももっともっとお伝えして意識を少しでもそういうふうにもってもらえるようになれたらなと思っております。
阿南 やっぱり私たち人間は危機に直面してはじめて目が覚めることって残念ながらありますけれども、もしいまが危機ならば、いまこそ目を覚ますときなんじゃないかと思うんですね。いい消費者になることが何よりも農家を応援するし、農家のみなさんのモチベーションも上がっていって、それがめぐりめぐって私たちの食の楽しみや健康になって戻ってくることだと思いますので、改めて食の魅力について今日は考える機会にしていただけたらありがたいなと思います。ありがとうございました。