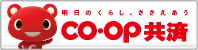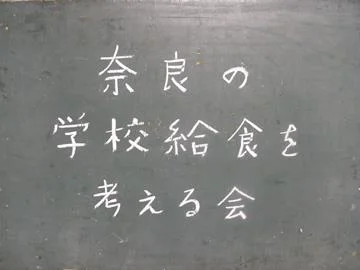2-3畑を耕してみる
(画像:株式会社粟WEBサイトより借用https://www.kiyosumi.jp/gokatani)
三浦 そうです。周りが畑ですね。
阿南 そして今日最初にあったように、その周辺もたくさんの遊休農地が年々増えていっている状況があるんですよね。
三浦 そうですね。私たちの、地域の場合は市街地近郊で、近鉄奈良駅から車で15分で移動できる場所にありますので、比較的ゆるやかだとは思いますが、実際に担ってらっしゃる方々の年齢を考えると、いま阿南さんがおっしゃったように、これからここの土地が空いてくるんだなというのはじわじわと見えてきつつあります。
阿南 そういうちょっと恵まれた場所でさえ、もうひたひたとそういった現実が近づいてきているなかで、逆に三浦さんはいままで農に携わってなかった人たちが農にデビューする、農的生活デビューをするチャンスにもなりうるんじゃないかともおっしゃっていますので、そのあたりのところ、食を提供されるシェフの立場も含めてお話伺っていいですか。
三浦 はい、ありがとうございます。実は阿南さんもいま畑の活動をしようということで「畑活」というキーワードで「さとびごころ」でもいろんな特集を組まれたりしてて、次の「さとび」も畑活がメイン特集になってるという……
阿南 はい、4月号の特集が「自分の食べものを育てよう」という特集で、「畑活」は本文の中には出てくるんですけれども、心を豊かにする農的生活ということでさせていただいていまして。なんと今回の主人公が三浦さんと非常にゆかりのある方で、文章の中にも三浦さんちらちらお出になられますので、よろしかったら楽しみにしてください。
三浦 魅力を伝えるための具体的な事例を2つお話させていただけたらと思います。私たちの清澄の里といわれる地域は、面積が200町歩あります。旧五ケ谷村という昭和31年に奈良市に合併した地域で、ちょうど奈良盆地から東の大和高原に上がっていくまさにその接合点です。なので平坦もありますし、中山間地、要するに山間もあるということで、たくさんの種類のものを多種多様に育てるには適していますが、大きな農業はできないという本当に日本の縮図みたいな場所です。ここで、このまま放っておくと遊休農地が増えてくることが予想されていたのですが、そういうタイミングで2022年からミシュランガイドにグリーンスターという認証制度が加わりました。今までは1つ星、2つ星、3つ星ということで、星が多ければ多いほど行く価値があるレストランみたいな格付けがされていましたが、そこにSDGsや持続可能なこれからの世界を構築していくために必要ということで、グリーンスターという新しい基準、要するに環境への視点をしっかり持っている、サステナブルである、それからフードロスやフードマイレージをしっかり考慮しているというような項目がそのなかに加わって、それが大きな価値となってきました。海外は逆に言ったら3つ星と同じぐらいグリーンスターがほしいみたいなかんじです。そういう飲食の側にも世界のトレンドが影響しているタイミングにも恵まれて、3つの課題を一元的に解決できるシェフズファームプロジェクトというプロジェクトを立ち上げてます。
(画像:さとびこサイトより借用https://satobico.jp/archives/967)
そのままなんですが、シェフがファーム、要するに農地を耕すプロジェクトです。どんなことをやってるかというと、奈良県のなかでも、もともとしっかりと食の魅力、農作物の魅力を食材としてPRされている奈良の食材に特化したお店がいっぱいあります。なかでも僕たちがすごく仲良くしているのが、学園前にある「ナチュラ」さんというイタリアンのお店。この方々が10年前からうちの畑を使って、遊休農地を耕して野菜を育てています。ここで、遊休農地は解消されます。彼らは魅力ある自分たちの食材を得られます。もちろんすべて無農薬と化学肥料を使わずに作っています。そこのルールだけは決めていますね。
2つ目のお店がこれも中国料理で奈良のなかでは予約がととれないことで有名な、ならまちにあります「枸杞(くこ)」というお店です。こちらも1つ星とグリーンスターを獲得されています。こちらのお店のオーナーである宮本さんご夫妻はシェフズファームプロジェクトに参画して4年目ということで、奈良の伝統野菜だけではなく、中国野菜もいろいろと育てて、さらにそれの種も採ってということをやっています。
3つ目が和食の名店「白(つくも)」というミシュラン2つ星ですね。奈良最高峰の和食だと思います。こちらのオーナー西原さんご夫妻も加わって無農薬で野菜作りに取り組まれています。
みなさん元々友達でしたので、信頼して一緒にプロジェクトに取り組んでいます。
魅力を伝えていくときに、まずここで2つポイントがあって、まず我々のようにレストランをやってるところは、当然お店にお客さまが来てくださいますので、そこで野菜や食材の魅力をダイレクトに伝えることができます。ところがこのスキームってもうひとつ広がりがあって、実は飲食店をやってなくてもだれでもできるんですよね。自分のおうちでホームパーティするときに、だれか県外の友人をお迎えするときに、どんどん使えちゃうと思います。やってる方も多いと思います。これは奈良の農作物の魅力を伝えるひとつのヒントになるんじゃないかということで、そのエッセンスの部分をお話しさせていただきました。