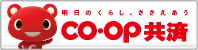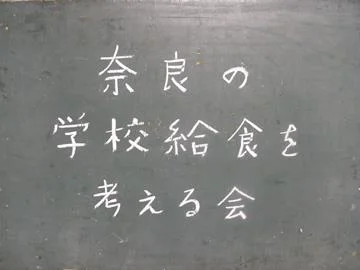2-2食から伝わるもの
阿南 ありがとうございました。それでは今日の話題に入っていきたいと思うんですけども、オオニシ先生は普段いろいろ講座をなさっていまして、講座のなかで実際にお食事を作って生徒さんと一緒に食べたりしながら、三浦さんのほうはレストランとしてお客様にお料理として提供するということで、おふたりとも「食べる」っていう共通項があられるかと思うんですけれども。その「食べる」っていうことをこれからどう膨らませていくか、それも単なるグルメではなくて、いま危機的な状況が迫ってきているなかで、それをふまえた上で大丈夫なのかって。それを眉間にしわを寄せないで、笑顔でやっていくのにどうしましょうかと。そういったお話が今日できたらいいかなと思っています。
まずオオニシ先生なんですけども、32年間もヨーロッパにいらして、いま奈良県の長谷、桜井にいまいらっしゃるんですね。どうして奈良をお選びになったんでしょうか。
オオニシ 日本でも同じように大騒ぎになりましたけれども、チェルノブイリだけじゃなく狂牛病だとかダイオキシンとか、その頃から本当に食の問題が社会問題として大きく出てきましたね。ヨーロッパが統一されて、それまでは国境を超えるのもいちいちビザをとって大変だったのですが、ひとつのユーロになりましてからただの県みたいなかんじで自由に出入りできるようになりまして、私もベルギーだけじゃなくフランス、オランダ、ドイツ、イタリア、イギリスとあちこち1か月5000km車を走らせてる、毎月オイルチェンジするみたいな忙しい生活に変わりました。みなさんの食に対する意識が変わったんですね。
私がなぜ食に関わるようになったかというと、もともと自分の手荒れがなかなか治らなかったんですが、当時マクロビオティックの講座にご縁がありまして、桜沢里真先生にお料理を習い、そこで食と体の不調の関係をとことん研究してた大森英櫻先生という方から直伝で習って、人生観が変わってしまったんですね。それまでインテリアデザインの仕事をしてたんですけど、私のやってきたことなんてゴミみたいなことに違いないというところまで行きついちゃいまして、食のほうにはまってしまいました。それからヨーロッパに行って人のおせっかいまでするようになってしまったということなんです。
2011年東日本大震災が起きてはっとしたんですね。なんとかくも長くいたことかと。それでもうこれからは日本のために頑張らなきゃいけないってことで、どこに帰ろうかなっていうことだったんですけど、それまで石造りで山もないぺっちゃんこのところに長い間住んでいたので、山がある木の古民家に住みたいな、日本的なところに住みたいと思って、はじめ京都と思ったんですけど、なんか違うなというかんじになりまして、じゃあ奈良がいいかなと思いました。
阿南 ありがとうございます。ようこそ奈良へ。マクロビオティックには身土不二っていう概念がありますけれども、拠点は桜井ということで、食材も奈良のものをお使いになられることもあるかと思います。奈良の食の魅力っていうのをお感じになることはありますか。
オオニシ もちろんです。やっぱり食イコール食文化といわれるように、文化とつながっておりますし、とりあえずそれ以前の縄文までいけばそれも日本なんだなと思いますが、日本の国はいちおう奈良から都になって始まったわけですから、それを考えますと、日本の全国それぞれの特徴はあって、特産はあるでしょうけれども、食べ方に関しては奈良を中心に考えていくことでいいのではないかと思います。
わたしヨーロッパで32年もやっていましたが、私が習ったマクロビオティックがそのまま通じたかというとそうではなかったんですね。黒人もいるし白人もいるしアジア人もいるしというかんじで、いろんな体質、いろんな体調の人がごちゃごちゃに住んでるみたいなところがヨーロッパなんですね。ですから一通り、ひとつの答えが通用するということが難しいところがある。そこにいたからこそ、どうやってその人たちに適切なアドバイスができるかっていうことに四苦八苦してきたわけですけど、そのおかげで食の方程式と自分では言ってるんですが、この人にはこういうのがいい、こっちの人にはこういうのがいいというのがだんだん見えてきて、単に陰と陽で考えてたものがもっと幅ができました。向こうの人に陰と陽の説明をしても10年も15年も習いに来ててもまだ分からないんです。
阿南 それは西洋の人には難しいでしょうね
オオニシ ええ、それで、このままじゃただただ長引かせて、学びの時間が長すぎて役に立たないと思いましてね。数字で割り切って、陰にも3段階、陽にも3段階ある、それで例えば分かりやすくいいますと、お腹の調子が悪いっていっても便秘の人もいるし下痢の人もいますね。血圧の高い人もいるし、低い人もいる。その人たち一緒の食事にできないと思うんですね。それが病院とか学校では同じものを全部食べなさいみたいなかんじになっていることがだいたい非合理だということははっきり言えるんですが。それを私は、例えば便秘の人には程度の差によって3段階、反対側のお腹がゆるんでしまっているほうも3段階に分けてみました。野菜の選び方や塩塩梅、お料理もどうすべきかってことがいろいろ出てくるんですね。それを作り上げまして。端的にいうと、お野菜も7段階にお腹をゆるめるのか強めるのか、調味料もお腹をゆるめるのか強めるのか、血圧に関しても下げるのか上げる素材なのか、調理方法も火を使うか生で食べるか、その中間もあって蒸して使うのかって、全部7段階にしましてね。もちろん細かくいえば100通りあると思います。だけれどもそうしたら整理がつかないので、7段階に分けまして、それをあなたの体調の状態が7段階のどの段階かで、足して8になる数の食材や調理法を探すということで教えるようにしたんですね。そしたらすごく効率性を合理的な考え方を教育されてきた西洋人にはものすごくヒットしまして、みんながものすごく大喜び。分かりやすいっていってすごく受けちゃったわけです。
それでこれからっていうときに2011年の東日本大震災が起きて、私はなんとか役に立ちたい、役に立てることはないかと福島に自費で行きまして、誰も呼んでくれてるわけじゃないんですが、小学校や幼稚園にこちらから無理に押しかけで訪ねていきまして、これからはこういうものを食べて身を守らなきゃいけない。特に放射能の汚染に関して心配ですから、向こうで散々言ってきたわかめ、昆布、海藻類を摂りましょうって言ったんです。海藻がいかに放射能から身を守るかって私ちょっと確信をもってるんですけれど、それで昆布の黒焼きのおにぎりをたくさん作りまして、毎日のように自分も食べて、自分の身を守り、そして人々にもこれを食べましょうって勧めて歩いてきたんです。
けど資金が尽きちゃったんで、また一度ベルギーに帰りまして、生徒さんと一緒にオランダの首都のデン・ハーグで玄米弁当とか昆布の黒焼きとか話題になっている放射能の汚染に関してのこういうふうにするといいですよってお弁当を作って売って資金を作って、また福島に行ったりしてたんですが、もう自分が日本に帰ろうと思いまして、帰ってきたわけです。それで奈良にご縁があっていま奈良から発信してやってます。
だからなぜ奈良にしたかって言ったら、やっぱり日本というものは特殊なような気がするんですね。向こうで暮らしてたからこそ思うんですが、日本にはいいものがたくさんあるので、それを現代の生活に合ったものとして発信していく地として選んだわけなんです。まずは日本と思って、いま日本国内にやってるんですが、やがて私の寿命がまだ許されるならばもう一回世界に発信していくつもりです。前はヨーロッパだけやってたんですけど、世界中に通用するひとつの論理、食に関する簡単な論理ですけども、自分に合ったものをどうやって探しとるかということなんです。
阿南 世界があって、日本があって、桜井がある、奈良があるということで、先生はおそらく狭い意味での奈良ではなくて日本の象徴的な場所として伝統文化が残っている、伝統野菜も残っている、そういう場所をお選びになったのかなと思いました。今度は三浦さんのほうですけれども、野菜を中心に伝統野菜のあるところには、いろんな意味で地域の豊かさとか健康とかいろんなものが含まれてるということを、本当にプロジェクトを始められたころから一貫しておっしゃっているんですけれども、その食べ物を提供されるレストランのすぐそばで畑がおありなんですよね。