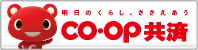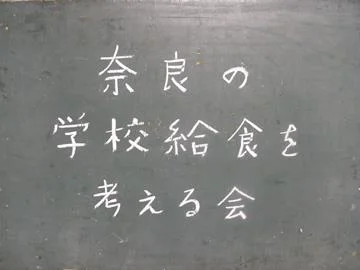2-1自己紹介
阿南 阿南セイコと申します。奈良を取材して、奈良の人に伝えるための、百年住み続けたい地域を考えるちっちゃい雑誌を個人で発行しています。で、その流れで単行本化と言いますか、ご縁から生まれてきた本を、雑誌ではなくて、保存版としても本に残したいということで、ひたすら企画、編集、制作、企画、編集、制作っていうのを日々やっています。そのテーマが本当に今日のお話と重なるようなことをばっかり載っていまして。やっぱり森林とか農業とか、自然と直接接するような産業、産業としてだけじゃなくて生き方とかライフスタイルとか、そういったものに染み込んでいくことがすごく大事だなって日頃から思っていますので、今日も素敵なゲストの皆さんとどんなお話になるか、とっても楽しみです。よろしくお願いします。
オオニシ やまと薬膳のオオニシ恭子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私は1981年から32年、私が習った(マクロビオティックの)桜沢里真先生の命で、体にいいお食事のあり方を教えていらっしゃいっていうことで、ヨーロッパの方に行きました。
ヨーロッパではベルギーというところに落ち着きましてね、そこを中心にゆるりと活動を始めたんですけども。私、それをお役目として、5年くらいやって日本に帰ろうという計画でのんきにやってたんですが、5年後の1986年にチェルノブイリの原発事故が起きましてね。周りが非常に戦々恐々という、一変してしまったんですね。そして私が日本人であるということで、「あなたは日本人で広島、長崎を経験して、原子爆弾を落とされて、それでもちゃんと生き延びてきてるっていうその理由は何だったの」「何を食べたの」ということで、あちらこちらからいろいろお話を聞きたいということがありまして、だんだん忙しくなってきました。
でも何食べたらいいのと言われても私自身が被害者だったという直接なものをもっていませんから、それ以前に日本にいるときに「こういう食事をしたら原爆の被害を避けられた」という、原爆症になっても治ったとか、そういう話はずいぶんありましたので、情報としては知っておりましたが。それがだいたい、玄米を食べて、わかめの味噌汁を飲んでということでした。だから私もみなさんに「玄米を食べてわかめの味噌汁を飲むといいらしいよ」というようなことをお伝えしたんですが、そしたら驚いたことに、向こうは海藻を食べない人たちなのに、その日のうちに日本食材店のわかめとかおみそが全部売り切れになるというのがあちこちで起きたらしいんですね。自分の言ったことが本当に正しいかどうか自分も自信がないままにそういう状況になったことにびっくりしちゃったんですけど。
それで私もだんだん真剣に考えなきゃいけないみたいな感じになりまして、いろいろ研究しているうちに、海藻が何にいいのか、玄米がどうなのかって真剣に考えるようになって、だんだん忙しくなってしまったわけです。で、あちこちからすごくいろんな問いがきますので、それに応えなきゃならないはめになって、結局それ以来32年も帰るに帰れない状況でみなさんのお世話をするはめになっていました。
2013年から奈良に住んでまして、というのは福島の事故がありましたね。東日本大震災ですが、それのために私はもうこれからは日本で福島のためにも頑張らなきゃと思って帰ってきて、いま13年になります。それだけじゃなく、いま日本のいろんな食の問題を考えますと、やらなきゃならないことがすごくあるなという状況で、いま奈良を中心に活動しております。
阿南 三浦さんお願いできますか。三浦さんは、実は私が作ってるマガジンに毎号載っていただいてるんですよ。一緒にトーク番組みたいなことを誌上でやってるんですけど、本屋さんで立ち読みでもいいのでよかったらまた見てみてください。
三浦 みなさんこんにちは。改めまして三浦でございます。本日はどうぞよろしくお願いします。今日の大きなテーマは「奈良の農作物の魅力を伝えるには」です。 阿南さんは「さとびごころ」の編集長でいらっしゃるので、普段は「編集長」とお呼びしています。 オオニシさんはご高名な方なのでお名前は何度もいろんな方からお伺いしてるんですけど、はじめてお目にかかります。
私自身はなぜここに呼ばれたかというと、おそらく農家レストランをしているので、奈良の農作物を実際に栽培していて、それをお客さんに伝えているからだと思います。私は「プロジェクト粟」というプロジェクトに取り組んでいまして、奈良市の中山間地域である「清澄の里」と呼ばれる地域をフィールドに年間約120種類のお野菜と10種類くらいの果樹、それからいろんな種類の薬草等を育ててます。
プロジェクト粟では、NPO組織で伝統野菜の調査研究や栽培保存を行いシードバンク活動にもとり組んでいます。また自分たちが農業をするだけではなく、地元の方々とも一緒に協同をしながら「五ヶ谷営農協議会」という集落営農の組織も運営しています。最後に「株式会社粟」で農家レストランの運営を行うことで、3つの組織を連携、協働し伝統野菜を地域資源に六次産業化に取り組んでいます。
農作物の魅力を伝えていくために私自身がどんなことをお伝えできるのかなということで、トークセッションの後半では、また具体的な事例みたいなものを2つほど挙げさせていただこうと思うんですけれども、伝統野菜の調査をちょうど30年ほどやってきた中で思うことは、お野菜をお野菜のなかのカテゴリーだけでとどめておくと魅力は伝わりにくいんじゃないかなということです。
奈良は食文化だけではなくいろんな魅力があるのではないかということで、2024年11月に『奈良のタカラモノ』という本を上梓させていただきました。
ここには奈良県発祥の歴史文化資源をひととおりまとめまして、それを食だけで終わらすのではなく、いろいろな観光とか伝統芸能とかを絡めていくことの有益性を提案しています。 いまガストロノミーということばがあるんですけれども、そういったようなアプローチで総合的に食を膨らませていく先に、食と工芸や地域とか観光のカテゴリーがだんだん薄らいでいって人間が生きる、暮らす、みたいなところが見えてくるのではないかなと思っております。
奈良県発祥の「発祥」には2つ意味があって、ひとつは「伝来」、もうひとつはそこから生まれたという「発祥」があります。食文化では、みなさんそうめんとか吉野葛とか柿の葉寿司はご存じと思いますが、それ以外にも実はいろんな食文化が奈良から発祥しています。これをいま申し上げたとおり、食と伝統工芸を掛けてツーリズムをするとか、食と歴史文化、要するに日本の文化の礎ですね、こういったものをミックスさせながら食の可能性を広げていくことがこれから食の魅力をつくっていくときに大切なんではないかなと思っているということをお伝えさせていただきたいと思います。