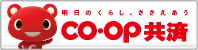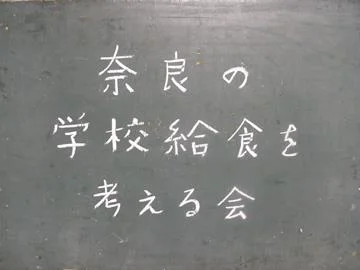1-4地域を巻き込む
山口 はい。実際にオーガニックビレッジ宣言をして有機農業を広めていって関心を持っていただくとしても、単に農業だけを見て広げようとするとやっぱり限界があると思うんですね。それは例えば野菜嫌いの人にこの野菜食べろって言い続けても食べないのと一緒で、何かそこにきっかけづくりっていうのが大切だと思ってます。
なおかつ広げる方法としても、奈良県の宇陀市っていうところが文化とか歴史がめちゃくちゃ深いところで、実はうちの農園の裏にも沢城という城がありましてね。この城は高山右近っていう武将さんが住んでいた城です。これは信長の時代、戦国時代の武将さんです。その方がいた地域なんで、最低でも1500年代ぐらいからはあったという地域なんですね。そういうところでずっとやってる中で、歴史や宇陀を発信することとコラボして農業をやればいいんじゃないかということで、室生寺さんとコラボしました。室生寺さんは女人高野とも言われてますけど、宇陀市は知らんけど室生寺は知ってるっていう人は結構おりまして、室生寺には国宝が3つもあって有名なんです。だったら室生寺さんとコラボしようということで。
うちでできた野菜の、廃棄野菜というのがどうしてもできてしまいます。スーパーでもオーガニックショップも綺麗なものしか売ってないと思うんですよ。虫穴のあるやつっていうのは全部廃棄になってしまう。それは勿体ないんで、それを加工して墨汁を作ったんですね。なんで墨汁かというと、元々ペーストを作ったんですけど、そのペーストが全く色落ちしないので、色が変わらないんだったら、絵の具みたいなできるんちゃうかってことで、野菜だけでできたんです。それを発信するのに、奈良って考えると、もちろん都があった文化ですから、書物があって墨の文化があると。だったらその墨を、野菜の緑で作れないかなっていうことでやったんですね。
(画像:山口農園WEBサイトより借用http://yamaguchi-nouen.com/category/6315.html)
で、出来たものを、室生寺さんとコラボしてお守りにしようということで作りました。実際今売ってるんですけど、再生和紙に野菜が入った墨汁で書いて、それを透明のアクリル板で挟んでます。そうすると中の紙が見えます。願い事が見えるんですね。願いが叶ったらそれをまた燃やしていただいて、また新しい願いをそこに入れると。くりかえし使えるサステナブルなお守りです。そのアクリル板も、コロナ禍で不要になったので例のアクリル板が、ダイセルさんとか富士電機さんっていう超大手の会社で倉庫に大量に眠ってると。それやったらコラボしましょうっていうことでそのアクリル板を工業高校の授業ではがきサイズにカットしていただいて、それをお守りのカバーにしています。宇陀を地域として盛り上げようということで、農業プラスそういったものをやれば発信力高まるんじゃないかなというふうに考えてます。
伊川 素敵ですね。いい香りがしてきそうな。お野菜の廃棄っていうのがやっぱりこちらにいらっしゃる皆さんだったら、穴が少し空いてても逆に安心の証の一つでもあるっていうふうに考えられるかもしれませんので、それが流通できないっていうこと自体は課題ではあるんだけど、でも大きな流通を変えていくっていうのはかなり大きな力がいるので、その中でやれることからっていうことで。でも逆にそういうことがあったんで、そういう文化とか歴史と繋がるきっかけになられたんですね。
山口 そうですね。バイヤーさんと消費者の方を比べると、消費者の方のほうが当然知識も理解力も高くて、どうしてもバイヤーさんになってしまうと綺麗なものでないと店頭に並べないっていう、そこの温度差があるかもしれませんね。
伊川 いや、でもこれは広がっていきそうですね。様々な各地のお野菜の墨汁があって、奈良で書画展みたいな
山口 でもなかなか紙に乗る墨汁て難しくて、うちのやつには実は抹茶をちょっとブレンドしてまして、それで墨汁がようやく完成したんです。
伊川 そうですか、お茶もちょっとお力添えを。なるほど。今おっしゃっていただいた、地域も一緒になりながら何か特産品を作っていく。そして歴史的なところでいくと縦軸ですよね。過去があって私達がいて未来に繋がっていくと。やっぱりそういったものにも思いをはせられるのは、この有機農業であったり農業の素晴らしいところかなと思いますね。
山添村には、神野山(こうのやま)という、関西で星を見ようと思えば、六甲を超えるかと言われている、素敵な「星降る羊の丘」という場所があるんですけども、その神野山の羊の取り組みを聞かせていただくことできますか。
野村 山添村のパンフレットの表紙がその「星降る羊の丘」ということで、山添村がいま一番売り出している観光地が神野山です。そこにめえめえ牧場(まきば)があって、羊を70頭ぐらいを飼っているんですけども。今は羊毛の羊なんですけども、数年前から増やしているのが羊肉の羊です。その羊肉も山添村の特徴を出そうということで、お茶の葉を食べさせて味付けしようっていう、そういう形の取り組みをしている段階なんです。ですから今はまだ完成していませんが、今年は試食をする機会を作ろうと思ってますので、もしその案内が出ましたら、多分数が少ないのですぐ売り切れると思うんですけど、ぜひともご参加いただけたらと思います。
山添村って神野山だけではなくて、実は知る人ぞ知る縄文文化からの歴史がありまして、縄文草創期の文化があるんですよね。そんなところから東大寺の杣山であったりとか、それからお水取りですよね。山添村に行くと二月堂の灯籠が3ヶ所ぐらいありまして、東大寺のお水取りに関係してる村だったんですよ。東香水講(ひがしこうずいこう)っていう講がありまして、それが東大寺のお水取りに関係してるってことだったんです。そういうものもこれから観光資源としていきたいなというふうに考えています。
ちょっと話が戻りますけど、山添村はオーガニックの野菜を作って、最終的には学校給食の食材として使っていけたらと思っています。もちろん今も地産地消でやってるんですけども、さらに有機農法の食材を増やしていきたいということ。それから将来的には、先ほど出てきた片平茜とか、豆蔵大豆っていう山添村特産の種がありまして、これの自家採種を広げていきたいなっていうふうに考えています。
伊川 ありがとうございます。本当にたくさんの素敵な情報をいただきまして、名残惜しいんですけど、これから農業者どんどん増えていったらいいな、有機農業どんどん広がっていったらいいなということで、最後にちょっと山口さんから一言ずつメッセージをいただけたらと思います。
山口 宇陀市もいろいろ進めてて、山口農園としても学校給食はずっとやってきています。外へ広げるばっかりじゃなくて、やっぱり地元の方に地域を知っていただく、無農薬とか有機野菜を知っていただくということを広めたいと思ってますし、やっぱり子どもさんって将来に向けて体をどんどんつくっていく時期ですから、毎日の食事の3分の1でもとても大事です。学校給食はずっと行ってて小学校の方はずっと体験もしていただいています。今年度からはこども園にも市の予算がつきまして、こども園でも食べていただいて、なおかつ体験もしていただいてます。
今年度初めてこども園さんの3歳とか4歳とかちっちゃいお子さんに体験していただくのに、そんな「SDGsは」とか言っても絶対聞いてくれないので、単純に種まきを、ちょっと指で穴開けて種を落とそうというのをやっていただいて。それはほうれん草だったんですけど、その種を落としたやつを、実際にできたら給食で食べていただいたということをやりました。簡単なきっかけでも、オーガニックに関わっていただくようなことを少しずつやっていきたいなというふうに思います。
伊川 ありがとうございます。子どもたちかわいいですもんね。
山口 そうですね、素直で純粋で。いつからこんなに心が濁ってしまうんかなと思って(笑)
伊川 (笑)ありがとうございます。野村さんお願いします。
野村 今日は本当にありがとうございました。山添村も実は去年の4月にこども園を開校しました。それから令和9年の4月を目指して小中学校統合して義務教育学校というのを作ることになっています。要はこども園から小中学校まで一貫した山添独特の教育をしていこうというふうに思っています。カリキュラムをかなり変えていこうと思ってるんですけど、そんな中で今年も伊川さんの方で各学校で有機の野菜も植えてくださったし、そういう学びをこれからもしていきたいたいなと思ってます。
それとやはり実際に作ったものを食べてもらえる機会っていうのはやっぱり大事だと思うんですよ。有機農法って言っても一般のと何が違うのって、味と香りが違うっていうことをやっぱりもうちょっと皆さんに体験してもらえるような場面を作りたい。今年10月26日(日)にオーガニックフェスタっていうのを山添村で開催しますので、そこではいろんな有機農法のものも食べられますので、ぜひとももしよかったらご参加ください。今日本当にありがとうございました。
伊川 ありがとうございます。ということで、これまたもう1回やりたいくらい楽しかったですね。最後に私の方から、広げていくための縦軸横軸のお話を最後にしようと思います。横軸の広がりってのはもう楽しさやと思うんですね。これは一億総農家じゃないけども、本当にみんなが土に触れ合うことは感受性も高くなるし、日本の文化を大事にしようという心も育まれるし、やって損はないので、みんなが土に触れていく楽しさ、これはもうどこまで広げてもいいと思っています。
そして縦軸は、山口さんに教えていただいたように、やっぱり農業で高みを目指していくこと。それは経営もあるので、より家族が幸せで笑顔になるためには経済的な豊かさと両方大切なので、そういった意味で奈良県の有機農業がレベルが高くなっていけば、どんどん注目されて、奈良の有機自然野菜って言ったらもう有名だよねってなると流通も変わっていくと思うので、縦軸もどんどんどんどん高めていきたいと考えてます。
我々「みんなとふるさと」としましては、今、山添村の方で野菜のオーガニックスクール、これは初級編が、若干10名弱応募できます。山添村の方優先ですけど、熱い方は村外の方も学びに来られますので、ぜひちょっとご検索ください。お米のオーガニックスクールは10名定員になっちゃいました。ただ、プロ向けオーガニックお米スクールは3回やります。これはもう奈良県を代表するプロのオーガニックお米農家の方みんな集めたいなと思ってるんですけど、そういった講座をやります。それから里山の学びや堆肥の学びっていうことで、いろんなスクールをこれからやっていこうとしています。それでは、つたないとこがあってお聞き苦しかったと思うんですけども、お2人のご協力で素敵な時間になりました。本当に今日の出会いを感謝したいと思います。ありがとうございました。