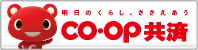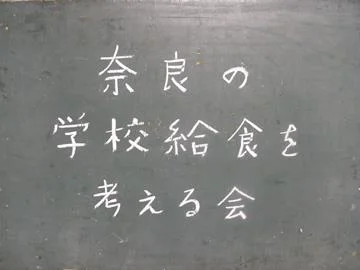1-3有機農業の学校
(画像:山口農園WEBサイトより借用http://yamaguchi-nouen.com/category/category/organic-aguri)
山口 はい、山口農園では2010年から「オーガニックアグリスクールNARA」っていう学校を運営しています。実は2022年オーガニックビレッジ宣言というのを、ご紹介あったように宇陀市が全国で一番にさせていただきましたので、それで今は一旦休校にしてます。というのは、農業の担い手を増やすっていったときに、オーガニックビレッジ宣言だからといって有機農家さんだけを増やすっていうのではなかなかこれハードルが高くてですね。いろんな方に来ていただくためには、うちが単独でそういった学校をするよりも、市が窓口を作って、そこにいろんな方に来ていただいて農家さんに繋ぐというような組織を作ったほうがいいなと。ということで今実は、毎月市役所で会議をしながら進めています。
「オーガニックアグリスクールNARA」というのは、ガチで有機農業で独立できる人を増やす、有機農業の入口としてやらせていただいていました。でも、有機農業を理想に来られても、実際にやってみたら全然違うかった、こんなしんどいものと思ってなかったということもありました。例えば草刈りですと、ずっと草刈りしてますから、「草刈りしに来たん違います」とかよく怒られたもんです。そういうようなところもあるんですけど、だからといってもう「あなたは農業向いていないですよ」じゃなくて、そしたら違う農業や、違う作物や、違うやり方・考え方でやれればいいんですよね。結局は農地が耕作放棄地化しなければいいと思うので。
伊川 ありがとうございます。そういった多様性のひとつとして私も呼んでいただいて、僕は葉物野菜を作ってるわけではないんですけど、「けんちゃんの考え方も伝えてあげて」っていうことで。本当に多様な方が学ばれてたのを今でも覚えてます。本当に大きな懐で、いろんな先生が目白押しで、あんなスクールっていうのはなかなか……
山口 学生さんもキャラの濃い人ばっかりで(笑)
伊川 全員ものすごく濃いです。質問がもうあっちもこっちも尖ってるんで。でも今もおっしゃったようにガチで有機農業で食べていこうっていう道で、1年にお一方……
山口 そうですね。学校は半年で、年に2回やってましたけど、結局その中で残るのは1人いるかいないかになってしまいます。
伊川 なるほどなるほど。ただ、残りの方々で僕が親睦のある方も結構いるんですけど、そういう方々も山口農園での研修を糧にされて、食の安全の道に進まれたり、地域活性化に尽力されている方がかなりいらっしゃるので。そういう意味では、「草刈りばっかりやん」とか、「もうずっと袋詰めせなあかん」とか、そういうリアルな農業を知った上で、それを支援する側に回るのか、調理や加工をする側に回るのかという話だともいえます。本当に素晴らしいスクールのあり方でした。
野村さんに伺いたいのは「YAMAZOEオーガニックスクール」では、一般の方々と公立の高校生が農業を一緒に学べると。昨年僕らも拝命いただきまして、33コマ実際に高校でオーガニックの授業をやらせていただいきましたが、かなり新しい取り組みだと思います。実は最初の圃場は野村さんが提供してくださった圃場だったんですけど、そこで一般の皆さんと、初めて農業する高校1年生の子たちと一緒に、有機農業の基本のきをされたご感想を伺いたいんですけど。
(画像:山添村立奈良県立山辺高等学校山添分校ブログより借用https://yamazoebun.exblog.jp/34133595/)
野村 私は仕事柄もあまり畑とか田んぼには手をかけられないもんですから、僕は綺麗に「自然農法」って言ってるんすけど、まわりからしたら「ほっとき農法」って言われても仕方がないような農法をしてます。要は肥料も農薬も入れずに、草刈りをしますよっていう形の農業です。ちょうどオーガニックスクールに提供した田んぼは一反ほどあるんですけども、多いときでも3俵、要は30キロが6袋しか取れないような状況で、もう株も細い細い株やったんです。
けど、提供してすぐにされたのが土壌改良。高校生と一般の方々が一緒になって、竹チップであるとか籾殻であるとか、いろんなものを入れられて、それから排水もされて、まさかここまでできるだろうと思ってなかったんですが、3ヶ月でそれはもう素晴らしい「大和ルージュ」というとうもろこしが500本できたんですよ。実は僕もその作業には関わったんですけど、手をかけるっていうだけでこんなにも変わるんやなってことを体感しました。
普段私は1人でやってます。ですから、トラクターするのも耕すのも全て1人で寂しく「あとちょっとやな」とか思いながらやってるんですけども、たくさんの人と一緒に汗をかくと、自然と笑顔が出てくるんですよ。やはりそれって農業する中ですごく大事なことなのかなって。
今まで僕の親父とかもやっぱり1人ではやってなかったんですね。若い頃は母親と、あるいはじいちゃんばあちゃんと一緒になって農作業する。あるいは近所の人。田植えでも何でもそうですよね。1人でやってなくて、昔は何人も並んで田植えしてたじゃないですか。今は機械があるおかげで1人でもできるようになったけども、それが逆に言うたら後継者を育ててないんかな。僕の息子にも本当はさせたかったんですけど、1人でもできるわっちゅう感じできてしまってるので、その辺が反省点かなと思ってます。
伊川 ありがとうございます。もう本当歩くだけで大変で、なんでこの田んぼなんやろかというような田んぼやったんですね(笑)。でも結果的にはすごくありがたくて。もし「種まけばできますよ」っていう畑だと「有機農業ってこんなもんか」ってなるのかなと。今回は歩くたびに長靴がすっぽ抜けるというようなところからやりましたので、講師の先生をお呼びしまして。その方は奈良の平坦部と高原部の境目で有機農業も慣行栽培も両方されている方で、まだ30代なんですけど、今回あえてその方にしたんですね。山口さんがおっしゃってたように、多様な農業があっていいんだよと。全部正解だよ。そういう中で今回なぜ有機農業をやるかって言ったときに、慣行栽培の良さも知ってくださっている方にお願いしたかったというところがありました。そういったところでやっぱりいま野村さんにおっしゃっていただいた、一緒になって作業する楽しさみたいなのは大事ですよね。
昨日も実はソラマメの手入れと人参の種まきをしてたんですけど、お兄さんお姉さん、おじさんおばさんみんなキャッキャ言いながら畑で楽しんでる。さかのぼって見ますと100年前は私たち、みんなで一緒に田植えをしてましたし、みんなで稲刈りもやってました。アンデスとかの少数民族たちはいまでも一緒にジャガイモを歌を歌いながら植えてるそうです。
田植えと稲刈り、僕らでいうと茶摘みとかはハレの日で、その他の手入れはケの日(日常の日)ということで、やっぱりみんなで集って共感共有し合いながら作物を収穫しているこういう喜びは、おそらく他の分野でなかなか代えがたい、人間としての必要な欲求を満たしてくれて、調和とか和の精神を作ってたんじゃないかなと思います。
新規就農されてお一方で畑されてる方はよく見かけるんですけど、山口さんのところは「山口農園グループ」としてみんなでチームを作りながら農業ができる仕組みをつくってらっしゃいます。そういう意味では、楽しい職場ですか。
山口 うん、そうですね。うちのグループが今ちょうど11人独立した者がいてまして、やっぱり農薬を使わないってことは非常に大変な農業だと思うんですけど、そうするとどうしても孤立化してしまいます。例えば有機農業ですと草刈りが大変って言いましたけど、草刈りをずっとしてると、周りが見えないんですよね。知らない間に村の行事をやっていて、周りから「なんであいつ参加しないんだ」と怒られて、だんだん温度差が出てくるっていうことがあって。それはそのことを気づかなかった、もう毎日作業で必死で情報が入ってこないというところがあるので、うちがグループ作った理由も、いろんな独立しやすいためのフォローをするためということです。
例えば、売れなかったらお金にならない、生きて食べていけないということなので、売り先を探すのに困る場合はうちの販路で買い上げることで売り先をフォローするとか。つまり担い手を増やして農地を守っていくためには、やっぱり出口を考えないといけないかなとは思ってます。
伊川 すごいですよね。僕も19歳で就農したときに、まず畑を借りてくる交渉力というか、やっぱ最低限の愛嬌っているんですよ。ものすごい無愛想な若者には農地貸したくならないんで(笑)。それから聞く力も必要で、やっぱり一方的な人には貸してもらえない。要するに、愛嬌がそれなりにあって、聞く力もあって、それから体力も要りますね。草を刈り続けて見えなくなっちゃうっていうのも、刈り続けられる人だけが達する領域で、まずは30分やってもしんどいっていう人はなかなか難しいし、作物を育てる計画性も必要ですよね。
山口 必要ですね。
伊川 ですよね。僕も最初レタスの種を買ってきて、大体1袋やから1回分やろうと思って撒いてみたら、もう3万株ぐらいのレタスの苗ができてしまって。それを全部植えないといけないなと思って植えたら畑中玉レタスになってしまって。流通を持ってなかったんで、必死で団地に配りに行ったっていう苦い思いがあるんですけど。今みたいなことは、山口グループでは起こらない……
山口 そうですね(笑)月に1回集まって計画からやってます。例えばうちから小松菜(の受注)が1000キロありますっていうと、グループの方たちが「100キロします」「200キロします」みたいな形で手を上げていくっていうシステムで。それは僕も農業始めたばっかりの頃に、パセリが人気なので有機のパセリを作ってくれってことで、ハウス2本分ぐらい作ったんですね。そしたらそのお客様から「もういらない」って言われて、できてしまったものがもうどうしようもないっていうことになったので、特に出口、つまり販路は大事かなというふうに思ってましたね。
伊川 やはりそういったご経験もされてきた中で、努力は必要だけど、体力もいるし、計画力います。それから帰ってきてものすごいしんどいのに帳簿付けないといけない、足らんときには借り入れもして、保証人はいないので自分で返さないといけないって、こういうものを全部クリアした人が新規就農で残るっていうふうに考えるとすごく難しい。それだけ難しいからこそ国は5年間150万円つけますよっていうふうにするんですけど。5年の後に残れるかって考えると、非常に少なくなってしまうんですね。そのあたりを鑑みたときに、「オーガニックアグリスクールNARA」からの山口農園グループっていうのはすごく考えられてると思いますし、本当の意味で農業者を増やすためには、こういった仕組みを国が率先してやるぐらいのことが必要だと思います。
おそらく今山口さんから伺った話っていうのは、やっぱり農「業」として、一つの産業として本当に残したければ、山口農園さんの取り組みをトレースして全国に展開するぐらいのことをやらないと日本の農業は本当にまずいという話だと思います。ですけども、それとともに、先ほど野村さんがおっしゃっていた、みんなでやったら楽しいねんとか、宮﨑駿さんの故郷の風景みたいなのって、全ての国民のハートにあると思うんですね。それを維持していくために農業というものは絶対不可欠。そういった視点で、山添村の存在価値みたいなところと繋がってくると思うんですけども。今まさに繰り広げられているこのオーガニック講座から、思いをはせられてることってありますか。
野村 ちょっと講座からも離れるかもしれないんですけど、山添村も実は新規就農者を受け入れています。去年から1人入って、その方は本当に自然農法というか有機農業をやってはって、すごい実績を挙げておられます。毎日大阪から来てはるんですよ。そんなすごい方もいはるんですけど、私としては、実は山添村には空き家がたくさんありまして、空き家に移住したいという方々が200件以上あるんですよ。応募はあるんですけど、それがなかなか空き家を提供できないっていう現状があります。ただ、入りたいっていう人のコメントを見ると、畑で何か野菜作りたいっていうコメントがたくさんあって。そういう人たちが入ってくれたときに、周りにある畑であるとかさっき言ってたような荒廃地ですよね。そういうところを活用して、ちょっとでも有機農法に取り組んでもらえへんかなっていうのは思いがあります。
そこで今年はオーガニックスクールっていうところで学びをしてきました。これは高校が続く限り続けていくんですけども、もう一つ、近くに「J1タケダファーム」っていう乳牛を飼ってるところと、もう一つ羊を飼っている牧場があるんです。そこのフンを利用して、有機の肥料を作ろうっていうのを、来年度は考えています。山添村の方って、家で作っている野菜には農薬はほとんど使われてないんです。ただ化学肥料とかを使われてるので、それでは有機にならないので、村が提供するその有機の肥料を村民さんに安くあるいは無償で分配していって、それを使ってどんどん有機に取り組むような方々を広げていきたいなっていうのが今の考えているところです。
オーガニックスクールでも、ほんまに若い方や全く農業経験されてない方から、僕よりも遥かに上の80歳ぐらいの年配の方まで、一緒になって学んでるんですよね。昨日もその話になったときに出てきた言葉が「体のことを考えて最近有機のもの、体にいいものを食べるようになったんやけど、それを食べてるうちに、ちょっとやっぱり自分でも作ってみたいなっていう気持ちになってきてん」っていう。それってすごい嬉しいですよね。そういうふうな方々を増やしていって、山添村の有機を広めていきたい。もちろん慣行農法も大事やし、生計を立てるためにそこが大事なのは絶対否定はできないし、これからも村としては応援をしていきますけども、その一方で有機も進めていきたいなっていうふうなことがあります。
それから長くなりすいません、1人でやってて寂しいって話で、グループみんなでやったら楽しかったっていう話ですが。実は僕大西という大字に住んでるけど、大西というところで農家をしているのは8軒なんです。そのうち跡取りがいるのは2軒です。ですから6軒さんはもうちょっとこのあと厳しいんですけど、その8軒の仲間で「日野菜グループ」っていうのを作りました。みんなで日野菜を植えてやりましょうって。
それが今度日野菜から、片平あかねっていって山添村にしかできない赤い大根があるんですけど、それを作りましょうと。それを作るにはね、片平っていう大字に行かないと駄目なんです。その土地で作らないと片平あかねにならないので、わざわざその大西という場所から片平に行って、畑を耕してあかねを作っています。
(画像:奈良県公式WEBサイトより借用https://www.pref.nara.jp/58585.htm)
それから次に去年から始めたのは、蕎麦を作りましょうと。山添村に蕎麦打ちの名人さんがいはって、山添村でも蕎麦欲しいよな、しかも有機の蕎麦あったらいいよねっていうことで、蕎麦を作り出しました。これは多分僕1人だったらできなかった。6人8人の仲間がいて、一緒になったから今も継続して、「ほんまは自分の田んぼのことしたいんやけどな」って思いながらも招集がかかるといかなあかんなってことで、一緒になってやっている、そういう現状があります。
伊川 ありがとうございます。素敵なお話をお伺いさせていただいて、本当に三者三様で今日皆さんいろんなお話を聞いていただけてラッキーかなと思うんですけども。今のお話のくだりでちょっとだけ天理のご紹介でいうと、天理はオーガニックビレッジ宣言させていただくときに、宇陀市さんのようなスーパーに並ぶような葉物野菜を目指すっていうのは今の自分らには難しいというか、それを今目指すべきじゃないってなったんですね。
天理市は、福住という人口1000人の地域からオーガニックビレッジ宣言始めてるんですけど、できるだけみんなでオーガニックやろうよっていうのが特徴です。私が提案した三年番茶作りを冬にみんなで集まってやることと、もう1個ハーブを提案させていただいて。地域に合った種類を選別して、完熟堆肥とともに有機ハーブの苗をお配りさせていただいて、「今お野菜を植えてる横に10mの畝1本だけ増やしてハーブを作ってみませんか」という声かけをやって、いま2年目で20件の方が作られています。
(画像:福住村プロジェクトWEBサイトより借用https://www.tenrifukusumi.com/post/20240921)
伊川 これも実は山口さんのお義父様の山口会長からお知恵を拝借したところがあって。山口会長が大和当帰を広げられたときも、そういった形で地域で広げられた。いま野村さんおっしゃった片平あかねも、そういう土地性と繋がった地場野菜っていうものがやっぱり一番愛着も出てきます。ハードルが高いとみんなができないので、そういった地域の優位を取り戻していくっていうのも、やっぱり有機農業の大事なコンセプトかなと思っています。
有機の語源って、ググっていただいたら「臓器」って出てきます。有機っていうのは、オルガニクスっていうギリシャ語から来てると言われてるんですけど、結局全ての違う臓器は動きも役割も全部が違いますよね。でもその違うものが一体として機能している。これは有機的連携だというようなところが語源らしいんですね。
なので畑の中でおそらく微生物はそういうことしてくれてると思うんです。我々人間側が多様性を認め合いながら、きちっと機能する状態を作っていく。なので、オーガニックビレッジ宣言っていうのはおそらく深読みすると、そういう生態系を地域で取り戻してほしい。「オーガニック宣言」ではなくて「オーガニックビレッジ宣言」ってのは、そこに意図があるのかなってふうに、勝手に深読みをしています。
山口さんが行っておられる室生寺さんとの取り組みが、まさにオルガニクスに繋がる、有機農業から多様な関わり合いを生んでいくっていう取り組みの一つかなと思ってるんで、ちょっとご紹介いただければ。